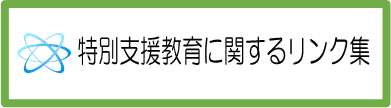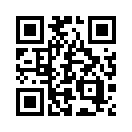校長ブログ
16.新年のスタート~巳のように~
校長室だより第16号です。お陰様で冬休み中児童生徒も職員も皆無事で、ひまわり教室もあすなろ教室も職員室も事務室も毎日元気に学んでおります。
本日8日朝、昇降口で元気に「おはようございます」「明けましておめでとうございます」のあいさつを交わして、新年のスタートを切りました。風邪等で体調が万全とはいかない児童生徒もおりましたが、インフルエンザやコロナに感染することなく、あすなろ教室もひまわり教室も全校集会を実施することができました。
今年の干支は巳、蛇です。集会で「巳年の巳という漢字は実とも読むので、コツコツ努力すれば、必ず良くなる。」と話をしました。児童生徒の話を聞く態度は本当に立派で感心するばかりでした。校歌を「我が山元に未来あり」の3番まで歌いました。元気に全校集会を迎えられたことを当たり前と思わないで、心から関係者の皆様に感謝いたします。
来週は入試があって新年度に向けた準備も本格化します。明日から給食も再開です。児童生徒の大好きなハンバーグやサバの味噌煮を食べて、平穏であることに感謝しながら、ゴールの3月13日(木)卒業式と3月24日(月)修了式を目指して元気に仲良く一歩ずついきます。
令和7年1月8日 山内
15.師走 ~今年を表す漢字はやっぱり「金」
校長室だより第15号です。師走に入り、日が暮れるのも本当に早くなり、今日はここ山元でも小雪がちらつきました。
12月3日に体育館で生徒会役員の任命式がありました。あれからもう一年、はやいものです。昨年も思いましたが、新役員一人一人に任命書を授与しましたが、みんな神妙な面持ちで、返事や挨拶からも役員としての決意が窺えました。聞いている中学部と高等部の生徒の姿もとても立派でびっくりしました。校長をしていてこのような任命式ができて、本当に誇りに思います。旧生徒会長から新生徒会長に腕章が引き継がれました。伝統は脈々と続いていくのでしょう。詳しい模様は写真付きで学校ブログに掲載されていますので、ご覧下さい。
12月6日には、地震・津波想定避難訓練が行われました。避難経路を確保し、第一次避難・第二次避難と段階を踏んで、しっかりと避難を完了できました。震災以来、様々な職場で地震想定の訓練を体験してきましたが、本校は本当に緻密に計画され、訓練もスムーズに行われています。防災主任をはじめ、先生方の尽力に頭が下がる思いです。「被災地」の学校としてこれからも防災教育に力を入れていきたいと思います。忘れた頃にやってきますが、能登は忘れないうちに災害が再びやってきました。
12月10日には、県庁やマナウェル宮城から指導主事を講師にお迎えし、ひまわり教室・あすなろ教室それぞれ授業を公開し全学部の先生方で勉強をする一日となりました。準備を進めてきてくれた先生方、特に授業を公開いただいた先生方に敬意を表します。
今日は1年をふり返る「今年の漢字一字」が「金」と発表されました。昨年は「税」でした。今年もいくつか予想されてましたが、パリ五輪での日本選手が多くの金メダルを獲得したこと、お金に関する事件事故も多かったこと等が理由だそうです。過去にオリンピックが行われた年は、日本人選手の活躍があって「金」という字が選ばれていて今年が5回目だそうです。毎日元気に仲良く一歩ずつ頑張っている本校の児童生徒一人一人に金メダルをあげたいと思います。来年がいい年であるように祈ります。冬休みまであと一週間です。
令和6年12月12日 山内
14.小雪 ~やっぱり寒くなりました 18日に初雪~
校長室だより第14号です。先週16日(土)と17日(日)の山元町は20度をはるかに超え、暑いくらいの日でしたが、週明けからは気温が一気に下がり、19日(火)には仙台で初雪が観測されるなど、やっぱり寒くなりました。それでも、お陰様で児童生徒はひまわり教室もあすなろ教室も毎日元気に学んでいます。
ひまわり教室小学部5、6年生は11月7日(木)、8日(金)いわき方面の修学旅行から元気に戻ってきました。気温は15度前後で天気も良く、泳ぐ魚を見たり、自分も泳いでみたり、美味しい物だけをいっぱい食べて、小学部での修学旅行の思い出ができました。小学部1年生から4年生は、11月15日(金)に校外学習で「八木山動物園」に出かけました。当日の仙台は心配された雨もなく、気温も16度ほどで、「やぎ、ひつじ、さる」とふれあい、子どもたちは動物園めぐりをエンジョイしてきました。映像でみるのと、実際に目にするのでは全く違った感じがしたはずです。
ひまわり中学部は全員そろって11月19日(火)に山元町内阿部りんご園に「リンゴの収穫」に出かけました。毎年お世話になっています阿部りんご園さん。気温はぐっと下がり肌寒かったですが、天気は良く、リンゴの収穫日和でした。大きく実ったリンゴを一人一人が、一個ずつ丁寧に収穫しました。山元町のリンゴは、宮城はもちろん、全国に誇れる美味しいリンゴです。中学部生徒達も自分でとったリンゴの味は格別だったはずです。私も生徒が収穫してくれたリンゴを食べようと思います。
高等部は職場実習期間中です。生徒も先生方も、校内外で実習に活躍中です。各教室では、実習のふり返り授業も行われます。実習の感想を発表するクラス、お礼状を書くクラス等、実習帰りの生徒たちからは、また一歩ずつたくましく成長した姿が窺えます。現場での成功も失敗も生徒一人一人の心に大きな動きを与えてくれるはずです。気がつけば、3年生の生徒たちは卒業まであとわずかです。
あすなろ教室は来週26日(火)に院内でふれあいコンサートが予定されています。「幸せなら手をたたこう」「糸」「もみじ」「レットイットゴー」和洋の名曲の演奏です。友達や先生方と歌や演奏をエンジョイします。これまでもこれからも、ひまわりもあすなろも豊かな情操を養う活動を続けていきます。
山元町では学校の近くにある「地球村」さんのアップルパイが有名です。昨年食べてみて本当に美味しかったので今年も食べようと思います。フルーツの町山元ですね。明日22日は二十四節気の「小雪」です。冬の到来ですね。23日は勤労感謝の日です。本校の子どもたちのためにご尽力いただいております方々に心から感謝いたします。
令和6年11月21日 山内
13.11月に入りました。~ハロウィン無事終了しました~
校長室だより第13号です。11月に入ってもう一週間です。お陰様で児童生徒はひまわり教室もあすなろ教室も毎日元気に学んでいます。
10月はひまわり教室中学部、高等部、あすなろ教室は天気にも恵まれ、各方面に修学旅行を終え、無事に学校に戻りました。良い思い出ができたことと思います。詳しい様子はHPをご覧ください。あとは、ひまわり教室小学部が今週末に修学旅行に出かけます。天気予報も良さそうです。楽しみです。
先週10月31日(金)にひまわり小学部17名の子どもたちがハロウィンの仮装をして「トリックオアトリート」と声高く校長室にやってきました。みんな元気にお菓子をもらっていきました。こちらも可愛らしい様子をHPでご覧ください。11月は小学部の修学旅行以外でも、施設体験や職場実習で小中高ともに校外での学習に出かけてきます。研修会や発表会、会議等で出かける先生方もおります。
いちじく、ぶどう、りんごと果物で有名なここ山元町は実りの秋を迎え、「名物」はらこ飯もいたるところで見受けられます。気がつけば今年もあと55日。明日は立冬です。今年の新語・流行語大賞のノミネート30も発表されました。一日一日を大事に「元気に仲良く一歩ずつ」過ごしていきます。
令和6年11月6日 山内
12.後期がはじまりました ~選挙と修学旅行です~
校長室だより第12号です。後期が始まってから、早いもので十日ほど経ちます。数日前から朝と帰りの昇降口で生徒会役員候補者が生徒に投票の呼びかけを行っています。国内も本校も選挙間近です。
今日は体育館で生徒会役員の立ち会い演説会がありました。高等部も中学部も、会長候補も副会長候補もとても素晴らしい演説でした。何度も練習したのでしょう。感心しました。聞く側の姿も本当に立派でした。先生方の支援をしっかりと受け入れて「やまりん」らしい一体感のある集会でした。選挙結果は気にしないで、当落関係なくみんなで良い学校を作りましょう。
さて、今週は「修学旅行週間」でもあります。中学部が関東方面に、高等部が関西方面にそれぞれ出かけます。天気の心配は今のところないようですので、楽しんでほしいと思います。明日は「霜降」です。昨日隣の岩手県で初霜、初氷のニュースがありましたが、ここ山元や関東・関西もまだ霜ではなく、露のままだと思いますのできっと良い旅になるでしょう。
本日からあすなろの校外学習で児童生徒は3班に分かれて角田中央公園へ出かけます。しかし、残念ながら、中止となる班もあります。来月あたりに再調整していけるといいかと思います。小学部の修学旅行は来月ですので、少し先となります。今は月末のイベント「ハロウィン」を楽しみに準備を進めているところです。「お菓子をくれないと、いたずらするぞ」と言えばお菓子がもらえて、本当に平和な国、平和な時代に暮らしていることに感謝しなければなりません。子どもたちが「トリック・オア・トリート」と来たなら「ハッピーハロウィン」と返したいと思います。
令和6年10月22日 山内